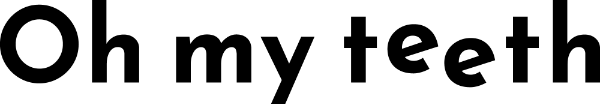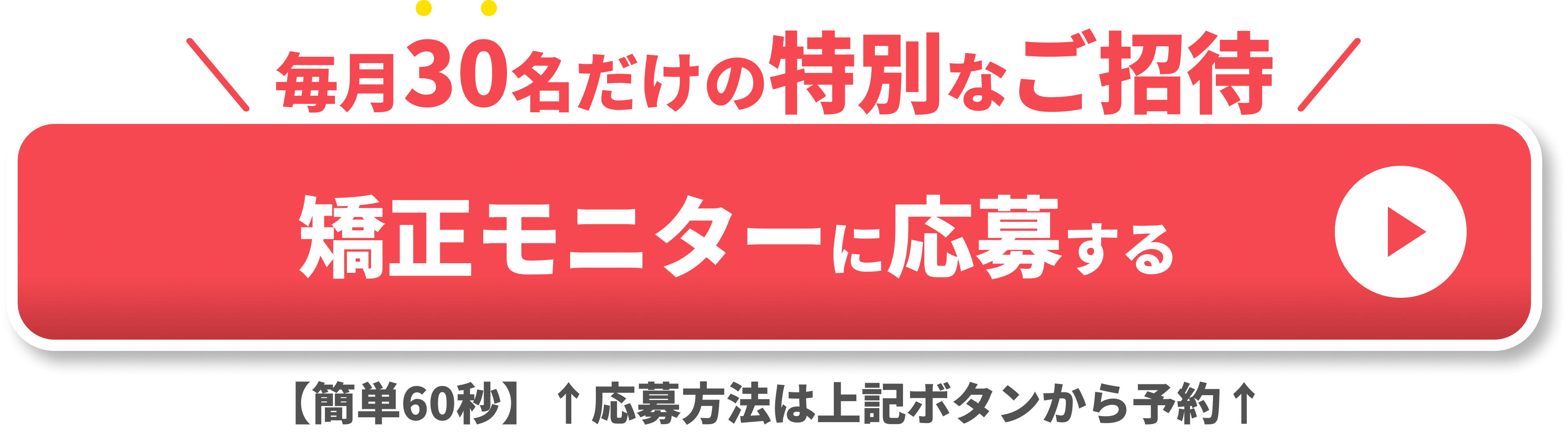歯科矯正
最終更新日:2025年8月8日
すきっ歯の原因とは?先天性・癖・骨格などタイプ別に解説

すきっ歯は一見ささいな見た目の問題に思えるかもしれませんが、放置すると噛み合わせの悪化や発音への影響、虫歯・歯周病のリスク増加など、さまざまなトラブルにつながる可能性があります。
本記事では、すきっ歯の代表的な原因から、放置することによるリスク、そして主な治療法までをわかりやすく解説します。
「見た目が気になる」「すきっ歯は治した方がいいの?」と感じている方は、ぜひ参考にしてみてください。

目次
- すきっ歯とは?
- すきっ歯の原因は?タイプ別に解説
- ① 歯のサイズ・本数による先天的要因
- ② 舌癖・口呼吸などの後天的な習慣
- ③ 上唇小帯や骨格など構造的な問題
- すきっ歯の原因を放置するとどうなる?
- 見た目のコンプレックスにつながる
- 虫歯や歯周病リスクが上がる
- 発音や滑舌に影響が出る
- 噛み合わせのバランスが崩れる
- 【原因別】すきっ歯の予防・対策方法
- 先天的な原因の場合
- 生活習慣に原因がある場合
- 骨格・上唇小帯に起因する場合
- すきっ歯の原因に関するよくある質問(FAQ)
- すきっ歯は自然に治ることもある?
- すきっ歯はかわいい?
- 子どものすきっ歯(発育空隙)は何歳までに自然に治る?
- すきっ歯の治療は保険適用される?
- すきっ歯の原因を知ることが改善への第一歩│まずは相談を!
すきっ歯とは?

すきっ歯とは、歯と歯のあいだに不自然な隙間が空いている歯並びのこと。
特に目立ちやすいのは上の前歯の真ん中に隙間ができるタイプで、「正中離開(せいちゅうりかい)」と呼ばれます。
また、前歯以外も含めて歯列全体に隙間がある状態は「空隙歯列(くうげきしれつ)」に分類されます。
なお、歯の隙間が2mm以上ある場合は歯科的な治療が検討されることが多く、見た目だけでなく機能面でも注意が必要です。
ただし、乳歯の時期に見られるすきっ歯は「発育空隙」とも呼ばれており、永久歯への生え変わりとともに自然に整うケースが多いため、基本的には経過観察で問題ありません。
すきっ歯の原因は?タイプ別に解説

すきっ歯の原因は一つではなく、先天的な歯や顎の特徴から、日常の癖や生活習慣まで、さまざまな要素が関係しています。
ここでは、すきっ歯の代表的な原因を3つに分けて詳しく解説します。
① 歯のサイズ・本数による先天的要因
すきっ歯は、生まれつきの歯のサイズや本数が関係しているケースもあります。
たとえば、歯が平均より小さい場合は、顎に対して歯が足りず、どうしても隙間が目立ちやすくなります。特に、上の前から2番目の歯が小さいときによく見られるケースです。
また歯の本数が足りない(先天性欠如)と、歯列全体に余白ができてしまうことも。2番目や5番目の歯に欠損がある例がよく知られています。
反対に、過剰歯(本来より多く存在する歯)が前歯の隙間に埋まっていると、歯の移動を妨げ、スペースが閉じにくくなる原因になることもあります。
② 舌癖・口呼吸などの後天的な習慣
すきっ歯は、日常の習慣によって後から生じることもあります。
たとえば、舌で前歯を押す癖や指しゃぶりがあると、前歯が少しずつ外側へ押し出され、隙間ができやすくなります。
無意識のうちに続けてしまうため、気づかないまま歯並びに影響しているケースも少なくありません。
また、口呼吸の習慣も注意が必要です。口が常に開いていると唇の圧力が弱まり、歯の位置が不安定になってしまうことがあります。
③ 上唇小帯や骨格など構造的な問題
前歯の真ん中にすき間ができる原因として、上唇小帯(じょうしんしょうたい)の付着位置が影響しているケースがあります。
これは上唇の裏にある筋のような組織で、通常は成長にともなって上へ移動しますが、位置が低いままだと前歯の間に隙間をつくってしまうのです。
また、骨格のバランスも要因の一つとして挙げられます。顎の幅に対して歯が小さい場合、並びきれずに歯と歯の間に余白が生じやすくなります。
すきっ歯の原因を放置するとどうなる?

すきっ歯の治療を放置することは、見た目に影響を与えるだけでなく、さまざまな悪影響をもたらします。
ここからは、すきっ歯の原因を放置するリスクについて解説します。
見た目のコンプレックスにつながる
すきっ歯は、笑ったときや話しているときに目立ちやすく、見た目に強い影響を与えます。
特に前歯の隙間は、清潔感や整った印象に直結しやすいため、気にする人も少なくありません。
そのため、人前で笑うことに抵抗を感じたり、写真を撮る際に口元を隠したりすることにつながることもあるでしょう。
虫歯や歯周病リスクが上がる
すきっ歯を放置すると、歯と歯の間に汚れが溜まりやすくなって、虫歯や歯周病のリスクが高くなります。
すきっ歯は隙間が広い分、歯ブラシの毛先がしっかり届きにくく、磨き残しが起きやすい状態です。
その結果、歯の表面や歯ぐきの境目に細菌が繁殖し、虫歯や歯周病が進行しやすくなります。
特に歯周病は、自覚症状が出にくいまま進行することもあり、気づいたときには歯ぐきの腫れや出血、ぐらつきといったトラブルを招くこともあります。
発音や滑舌に影響が出る
すきっ歯があると、発音や滑舌に影響が出ることがあります。
特に、前歯に隙間がある場合は、空気が漏れやすくなるため、サ行やタ行などの発音が不明瞭になることがあります。
さらに、口の中で舌や唇の動きが安定しにくくなることで、言葉がこもったり聞き取りづらくなったりすることも少なくありません。
噛み合わせのバランスが崩れる
すきっ歯を放置すると、噛み合わせのバランスが乱れる原因になります。
歯の隙間があることで、上下の歯が正しく噛み合わず、特定の歯だけに過剰な力がかかるようになります。
その結果、歯の摩耗やぐらつき、あごの関節に負担がかかるなど、口全体の機能に悪影響を及ぼすおそれがあります。
こうした噛み合わせの不調は、噛みにくさや顎の疲れ、さらには頭痛や肩こりなどの不調につながることもあるため注意が必要です。
あわせて読みたい

噛み合わせが悪いと出る症状は?放置するリスクと対処法を紹介
【原因別】すきっ歯の予防・対策方法

すきっ歯を改善するには、原因に合った方法を選ぶことが大切です。
ここでは、先天的な要因・後天的な習慣・構造的な問題(骨格・上唇小帯に起因する場合)という3つの視点から、それぞれに適した予防や治療法を解説していきます。
先天的な原因の場合
先天的な要因によるすきっ歯は、歯列矯正や補綴(ほてつ)治療によって改善が可能です。
生まれつき歯が小さい・足りない・過剰にあるといったケースでは、自然に隙間が埋まることはほとんどありません。
そのため、歯を並べ直す矯正治療や、隙間を補うための詰め物・被せ物など、歯科的な処置が必要になります。
矯正治療の場合は、マウスピース矯正やワイヤー矯正、補綴治療ではラミネートベニア、ダイレクトボンディングなどの治療法から、噛み合わせの状況などを総合的に判断して医師が選択することが多いです。
生活習慣に原因がある場合
舌癖や口呼吸などの生活習慣が原因の場合は、まずはその癖を見直し、改善することが重要です。
指しゃぶりや舌で前歯を押す癖があると、矯正してもすきっ歯が再発してしまうことがあります。
また、口呼吸が続くと唇や頬の筋肉が弱まり、歯が正しい位置におさまらなくなるおそれも。
これらの習慣は無意識のうちに続いてしまうことが多いため、意識してやめる工夫が必要です。
例えば、MFT(口腔筋機能療法)など専門的なトレーニングを取り入れることで、根本的な改善を目指すことができます。
骨格・上唇小帯に起因する場合
骨格や上唇小帯などの構造に問題がある場合は、歯列矯正や外科的な処置が必要になることがあります。
例えば、上唇小帯という上唇の裏のすじが前歯の間に入り込んでいるケースでは「小帯切除術」という処置で筋を切除し、そのうえで矯正治療を行うのが一般的です。
また、顎の骨の大きさや位置に問題がある場合には、矯正だけでは改善が難しく、外科手術を併用することもあります。
すきっ歯の原因に関するよくある質問(FAQ)

すきっ歯の原因について調べていると、「自然に治ることはあるの?」「子どもの場合は放っておいても大丈夫?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
ここでは、よくある質問を取り上げ、それぞれの疑問にわかりやすくお答えします。
すきっ歯は自然に治ることもある?
永久歯ですきっ歯になっている場合、自然に治ることは基本的にありません。
大人のすきっ歯は、歯のサイズや本数、骨格などが原因となっていることが多く、放置しても隙間が埋まる可能性は低いため、基本的には矯正などの治療が必要です。
一方、子どものすきっ歯(乳歯の時期)であれば、自然に治るケースもあります。これは「発育空隙」と呼ばれるもので、永久歯が生えてくるスペースを確保するために必要な隙間です。
年齢や歯の生え変わりの状況によって判断が異なるため、気になる場合は早めに歯科で確認してください。
すきっ歯はかわいい?
すきっ歯を「かわいい」「個性があって魅力的」と感じる人もいますが、見た目だけを優先して放置するのは注意が必要です。
例えばフランスでは、歯の隙間から幸運が入ってくるとされ、モデルや女優の中にはチャームポイントとしてあえて治療せず、そのままにしている人もいるとされています。
しかし、すきっ歯は見た目の印象だけでなく、虫歯や歯周病のリスクが高まったり、発音や噛み合わせに影響を与えたりすることも多いのが実情です。
すきっ歯を魅力ととらえること自体は悪いことではありませんが、健康面も含めて総合的に判断して治療を検討してください。
あわせて読みたい
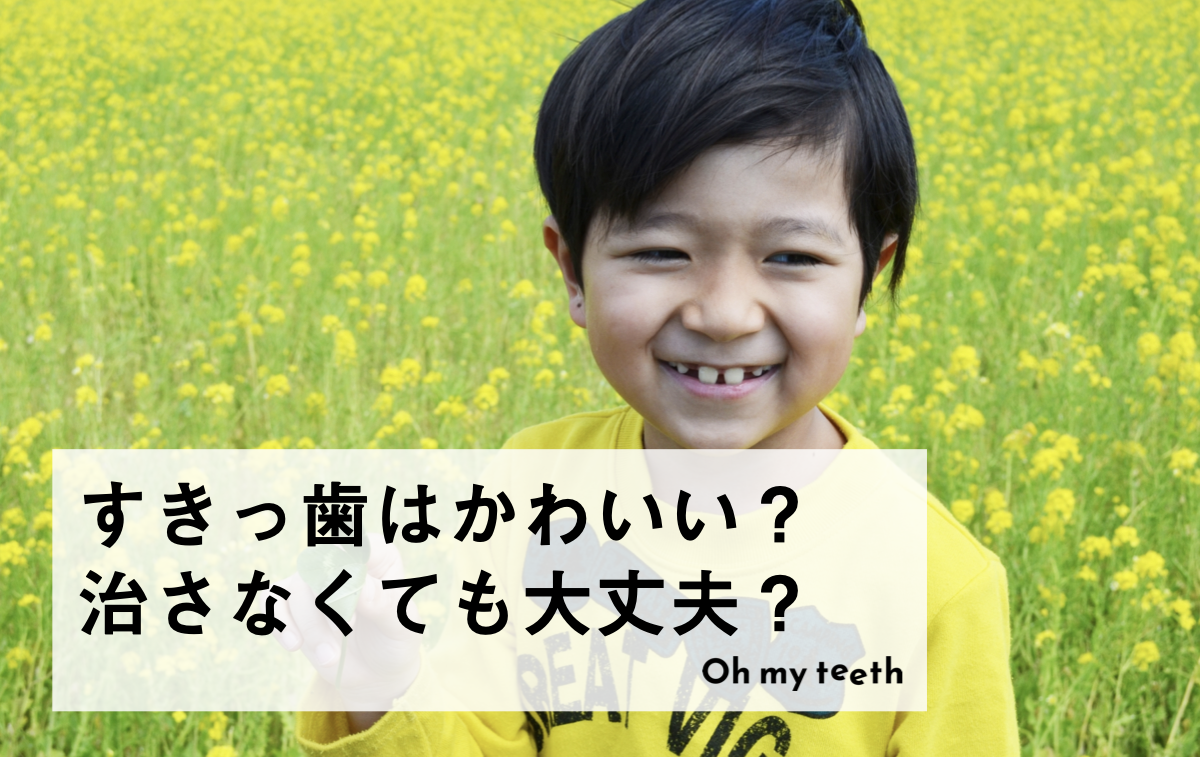
すきっ歯はかわいい?治さなくても大丈夫?
子どものすきっ歯(発育空隙)は何歳までに自然に治る?
個人差はありますが、子どものすきっ歯(発育空隙)は前歯が生えそろう10歳ごろまでに整ってくることが多いです。
一般的には永久歯は乳歯よりもひとまわり大きいため、永久歯が生えそろうことで、自然と隙間が埋まります。
しかし、乳歯の時期に歯と歯の間に全く隙間がないと、永久歯に生え変わる際に十分にスペースがなく、歯並びがガタガタになるリスクも考えられます。
気になるようであれば、そのままにしておいても問題ないかを、歯科医師に相談してみましょう。
すきっ歯の治療は保険適用される?
すきっ歯の治療は、原則として保険適用外(自由診療)です。
見た目を整えることを目的とした矯正治療や補綴治療(被せ物・詰め物など)は、美容目的とみなされるため保険の対象にはなりません。そのため、費用は全額自己負担となります。
ただし、噛み合わせや咀嚼に明らかな支障がある場合、あるいは顎の変形など医学的に治療が必要と判断された場合には、一部のケースで保険適用となる可能性もあります。
適用条件は限られているため、気になる方は歯科医院で相談してみてください。
あわせて読みたい

歯の隙間を埋めるのは保険適用になる?すきっ歯の費用を抑えたい方へ
すきっ歯の原因を知ることが改善への第一歩│まずは相談を!

すきっ歯は、歯のサイズや本数の問題だけでなく、舌癖や口呼吸などの習慣、上唇小帯や骨格など、さまざまな要因が関係しています。
自己判断では原因を特定しにくく、間違った対策を続けてしまうと、かえって悪化してしまうこともあります。
そんなときに役立つのが、マウスピース矯正サービス「Oh my teeth」の無料カウンセリングです。カウンセリングでは、自分のすきっ歯の原因や適した治療法について歯科医師から直接アドバイスを受けることができます。
気になる隙間を治して、笑顔に自信を持ちたい方は、まずは気軽に無料相談からはじめてみてはいかがでしょうか。